今回は、そのぎっくり腰を最短で改善するストレッチ体操を紹介します。
いつ起こるか分からないぎっくり腰に、もしなってしまった時に整体師が行う最善の対処法をお教えします。
今、ぎっくり腰で悩んでいる人はぜひ参考に取り入れてみてください。
何気ないことで起きるぎっくり腰の原因と3つの要因
厚生労働省の調査によると原因が特定しきれない腰痛は85%もあるというのです。
[skillwrapper type=”circle” track_color=”#dddddd” chart_color=”#ff6e8d” chart_size=”150″ align=”center”] [skill percent=”85″ title=”原因が特定しきれない腰痛”](資料出所:What can the history and physical examination tell us about low back pain?
JAMA 268: 760-765, 1992 )[/skillwrapper]原因が確定できる特異的腰痛は、医療機関を受診する腰痛患者の 15%くらいの割合といわれています。引用元:腰痛対策 – 厚生労働省
ではなぜ、ぎっくり腰が起こってしまうのでしょうか、当院(きたの均整院)に来院される患者さんからアンケート調査をしたところ、大きく3つの要因によるぎっくり腰が発症していることがわかりました。
要因1.内臓の冷え
[skillwrapper type=”bar”] [skill title_background=”#ff6e8d” bar_foreground=”#ff6e8d” bar_background=”#eeeeee” percent=”35″ title=”内臓の冷え”][/skillwrapper]アンケート 42人/120人 きたの均整院調べ
腰と内臓はとても密接な関係にあります。内臓の背面は腰ですよね。
胃や腸などの内臓は直接、腰椎脊髄神経とつながっていますので、お互いに影響し合います。
ですから、夏の時期に冷たい飲み物を飲み過ぎて、お腹を冷やすと腰も冷えてしまいます。
季節の変わり目に、ぎっくり腰が増えるのも内臓が冷えていることが原因で、何気ない動作の負担だけで「ぐぎっ」と腰が砕けてしまうのです。
また腰痛を繰り返す人は、便秘になりがちです。腸と腰の関係性が深いことが言えます。
要因2.気を抜いた時の腰骨への強い負荷
[skillwrapper type=”bar”] [skill title_background=”#ff6e8d” bar_foreground=”#ff6e8d” bar_background=”#eeeeee” percent=”30″ title=”腰骨への負荷”][/skillwrapper]アンケート 36人/120人 きたの均整院調べ
いつものしている何気ない動作で、急にぎっくり腰になってしまった経験の方もたくさんいます。
体を急にひねった時や、床の荷物を持ち上げようとした時、くしゃみや咳などで、突然腰に激痛が走ります。
実は、何気ない動作でも物を拾うという動きは、腰に大きな負荷がかかっているのです。
前かがみに体を倒すだけでも、重心は腰に体重の約50%のしかかってきます。
体重60kgの方だと30kgが腰にかかります。
気を抜いているときは、体は脱力状態です。
そんな脱力状態時に、重心移動があればなおさら、腰骨や椎間板に負担がくるのは当たり前なのです。
腰の予防には体幹トレーニングが必要だと医者から言われるのはこのためです。
要因3.長時間の姿勢が腰を固める
[skillwrapper type=”bar”] [skill title_background=”#ff6e8d” bar_foreground=”#ff6e8d” bar_background=”#eeeeee” percent=”20″ title=”長時間の姿勢維持”][/skillwrapper]アンケート 24人/120人 きたの均整院調べ
デスクワークやしゃがみ仕事、立ち仕事など同じ姿勢を長時間続けていると腰の筋肉は疲労物質が溜まりで固まってきます。
固まった腰の状態で、急に動くと体がついていけず、腰に衝撃が走ります。
長時間座ったり、しゃがんだ姿勢から立ち上がろうとするときに「腰が伸び切らない」と感じた経験もあると思います。
腰痛の常識が変わりつつある!意外に多い間違ったぎっくり腰の対処していませんか?
では、もしもぎっくり腰になってしまった時の対処はどのようにすればよいのでしょうか。
間違った方法で対処してしまうと、何週間も長引いたり、またぎっくり腰を繰り返してしまう体質が身についてしまいます。
急性期はお風呂でゆっくり温めるのは絶対NG
ぎっくり腰を発症してしまい、何もできず気持ちだけ焦ってしまいます。
「明日も仕事だし、早く改善したい!お風呂で温めてみたら少しは良くなるかも!?」
これは大間違いです。
ぎっくり腰は何らかの原因で腰骨、椎間板に「急性の炎症」を起こしている状態です。
炎症を起こしているということは、すなわち熱をもっていますので炎症を抑えるためにも冷やさなくてはなりません。
ただし、冷やし過ぎる処置は気を付けなければなりません。例えば氷枕などで直接患部に当てたり、長時間当てるのは返ってよくありません。
氷枕、アイスパックなどを直接長時間当てすぎると内臓まで冷やしてしまう恐れがあります。
腸と腰は密接な関係があると言いましたが、お互いに悪影響が生じてきます。氷で冷やす場合はせいぜい10分くらいまでとしましょう。
冷やす処置で良いとされるのが、冷湿布をこまめに張り替えることです。
冷湿布の効き目が薄く感じたら、張り替えてひんやりと思う程度で炎症を抑えることが大切です。
では逆に、急性期にお風呂などで温める処置を行うと
ぎっくり腰を発症して1日目~3日目の急性期にお風呂で、ゆっくり温める行為については痛みを助長させることになります。
確かに、ゆっくりと湯船で温めると、少し楽になったと感じることはあります。
血行が良くなり、筋肉がほぐれるからです。
ただし、危険なのは”湯冷め”です。
風呂から出たら体は徐々に冷えてきます。冷えてくると、その熱は身体の炎症患部に集まってきてしまいます。
ということは、ぎっくり腰は腰に熱が集中して、ズキズキ痛みが増してきてしまうということです。
熱を持った炎症状態に温め行為は、危険です。
打撲やねんざも同様で炎症をもって腫れてきた足に温めたりはしませんよね。
必ず冷やして熱を抑えますよね。
腰も同じです。ただし、冷やし過ぎには注意しましょう。
間違った腹筋や体幹トレーニングをしていませんか?
「腰痛」=「腹筋の弱さ」という原因の認知は、広がってきているように思います。
確かに、この考えは間違っていません。
ただし、腹筋の仕方が大切です。
間違った腹筋の方法をしてしまうと、腰に負担を与えてしまい、余計に神経圧迫や筋肉炎症を強めてしまうからです。
こんな腹筋していませんか?
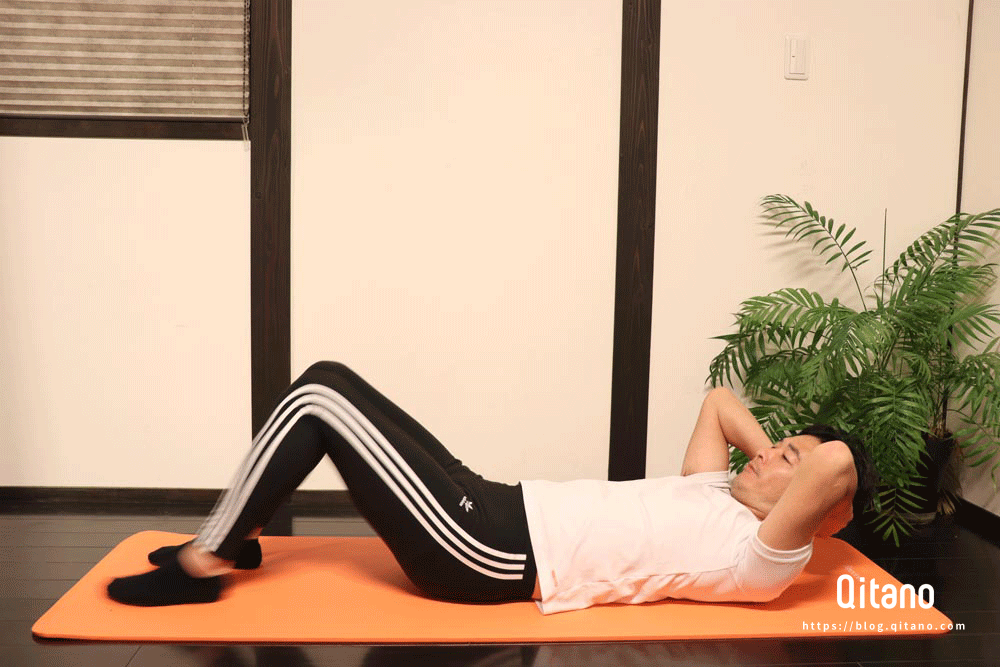
ぎっくり腰はにNGな腹筋
この通常よくある腹筋では、腰への負担が大きすぎます。体を起こす際に腹圧の衝撃が腰骨へ強すぎて痛みが発生してしまいます。
急性期には側筋トレーニングも腹斜筋などのひねる腹筋トレーニングもしない方がよいでしょう。
背骨に対して、無理のない適度な腹圧を感じさせる腹筋でなければ、腰のケアにはなりません。
負荷の強い腹筋トレーニングは、腰痛が改善してから行うようにしましょう。
まずは安静2日目からは適度な運動でぎっくり腰を改善することが大切
ぎっくり腰で受診した後、腰痛が3か月以上継続した人
[skillwrapper type=”bar”] [skill title_background=”#ff6e8d” bar_foreground=”#ff6e8d” bar_background=”#eeeeee” percent=”28.6″ title=”安静にした人”] [skill title_background=”#ff7ba4″ bar_foreground=”#ff7ba4″ bar_background=”#eeeeee” percent=”0″ title=”適度な運動した人”][/skillwrapper]
BS日テレ「深層NEWS」より
世界の多くの国の診療ガイドラインには、ぎっくり腰を代表とする腰痛が起こった場合は3日以上の安静は良くなく、痛みの範囲内で適度に動いた方が良いとされています。様々な研究結果から、3日以上安静にした人の方が、ふだん通り動いた人よりも、その後の経過が悪いことが分かってきたのです。腰痛への認識は、以前と大きく変わってきています。
腰痛の慢性化率は高いですが、信頼できる研究によると、腰痛でクリニックにかかった人の3分の2には、1年後も腰痛があるとされています。
今回、当院(きたの均整院)でどのような対処をしているか聞いてみたところ、「安静にする」「コルセットや湿布、痛み止め薬を使う」「整体院やマッサージ店に行く」など様々でしたが、一番多かったのが「ストレッチをする」でした。
実はこのストレッチはとても良いことで、腰痛を改善するのに効果的です。
逆にコルセットは腰の安静につながり、そのことがかえって細く弱い筋肉にしてしまいます。
安静のし過ぎは“百害あって一利なし”なのです。
ではどのような、対処やエクササイズを行えば、急性期のぎっくり腰を一日でも早く改善させることができるか、ご紹介いたします。
ぎっくり腰になったらまず安静「一日でも早く」最短で改善するストレッチ体操6選
【発症❶日目】安静にし炎症を抑える応急処置

タオル、アイスパック(保冷剤でもOK)
①準備:氷枕、もしくはアイスパックをタオルでくるみます。

ぎっくり腰を安静に冷やす体勢
②仰向けに寝て、両膝を立てます。
③痛みを感じる患部にタオルを巻いた氷を当てます。
当てる時間は、10分~15分まで
④その後は、炎症を抑える湿布薬を張り、安静に過ごします。
ぎっくり腰が完改善するるまで、毎日張り替えるようにしましょう。
⑤腰に負担のない安静な体勢で休みます。
- 両膝を立てて仰向けに寝る
- 両足に座布団や枕を置いて、足を高い位置にして寝る
- 左右の腰で、痛みを強く感じる側を下にして、横向きで寝る
シャワーでさっと体を洗う程度はOKですが、湯船につかることはやめた方が改善は早いです。
程度によりますが、お風呂に入らないだけでも翌日「意外と改善してる!」と驚くこともあります。
【発症❷日目~❸日目】「寝ながら」ストレッチ体操で柔軟性を取り戻す
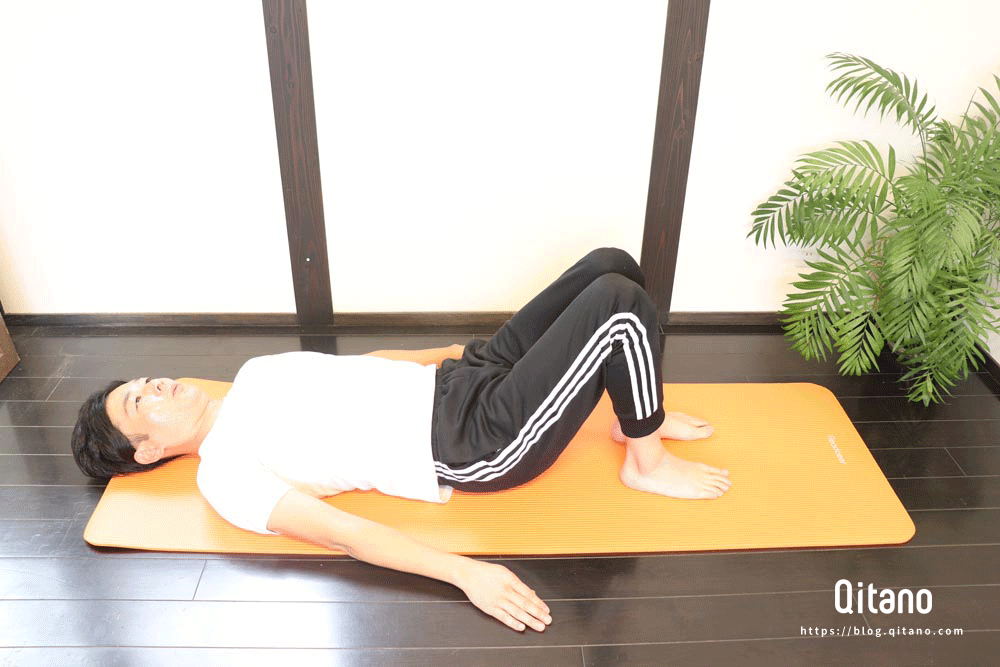
寝ながら骨盤ひねり体操
ストレッチ体操方法両膝を右にゆっくり倒して一呼吸します。
反対も同様に左にゆっくり倒して一呼吸します。
回数左右交互に5回×2セット
ポイント腰や骨盤が硬いと、両膝を倒したときに肩が浮いてしまいます。
少々浮いても大丈夫なので、腰や骨盤が伸びている感覚をつかみましょう。主に骨盤内の腸腰筋という筋肉のストレッチ体操となります。
腸骨筋の解剖図を動画で簡単解説
両膝を左右に倒す体操は、骨盤のねじれを解消する効果があります。
また倒した脚を逆へ移動する際に、腹直筋や腹斜筋群(腹筋の横の筋肉)などの体幹トレーニングになります。
産後に垂れ下がるぽっこりお腹を引き締める効果があります。
【発症❷日目~❸日目】「小さな腹筋」で腰骨の並びを整える

腰痛運動【腹直筋上部の小さな腹筋運動】
腹筋上部に意識を置き、効いている感覚があれば出来ています。
腹直筋の解剖図を動画で簡単解説
腹直筋上部の体幹トレーニングとなります。
通常の上半身全身を起こす腹筋は腰に大きな腹圧負荷を与えてしまい、余計に痛みが増す場合が多いです。
しかし、この肩甲骨が浮く程度の小さな腹筋だと、腰に負荷はなく腹直筋を鍛えることができます。
ぎっくり腰の痛みがあっても、この小さな腹筋運動であればできるでしょう。
また腰骨の並びも整いやすく、腰痛全般におすすめの体幹トレーニングです。
【発症❷日目~❸日目】「腸もみ」で内臓の緊張を和らげる

腸をもむ位置

ぎっくり腰改善の腸もみ体操
姿勢仰向けに寝ても、座っても、立って行ってもどちらでもよい。
ストレッチ体操方法左手で左の肋骨の下、右手で右の腰骨のあたりをギュッとつかみ、ゆっくりもみほぐす。両手とも上下を入れ替え、合計3分間行う。
回数3分間×2セット
ポイントゆっくりじわっとほぐすことが大切です。
自律神経で動く腸(内臓)ですから筋肉と違い優しくゆっくりもむことで効果が得られます。強く激しくすると逆に腸が炎症を起こしてしまうので気持ち良く感じる程度にしておきましょう。
腰痛を持っている人が便秘が多いように、腸と腰は密接な関係があります。
腸をじわっとほぐすことによって、「腸の働きが改善」→「便秘が改善する」→「腰椎神経の交感神経の緊張がほぐれる」→「腰の筋肉、靭帯がほぐれる」というサイクルがうまれます。
特に、股関節周りの左右2点は便がつまりやすいので重点的にするとよいでしょう。
【発症❸日目~❼日目】「片脚寄せ反発~脱力」ストレッチ体操でPNF効果

腰痛のPNFストレッチ体操
姿勢仰向けに両膝を立てて寝ます。
ストレッチ体操方法
①両手で右足を右胸に引き寄せます。
②右を足を元のあった場所に戻すように力を入れて反発しあいます。5秒息をとめて耐えます。
③5秒経ったら、全身一気に脱力して、足をストンと元の位置に戻します。
④逆の左足も同様に、左胸に引き寄せた状態で5秒息をとめて脱力します。
回数左右交互に5回ずつ×2セット
ポイント反発しあって力を入れているときに、腹筋を締めて(力を入れて)行いましょう。
手をパッと放してあげても大丈夫です。パッと反した方がPNF効果があり、脱力した時に腰回りの筋肉が緩みます。
5秒耐えることがきつい場合は、3秒でも大丈夫です。ただし、腹筋は力を入れておきましょう!
腸骨筋の解剖図を動画で簡単解説
腰の筋肉を効率よく緩めることができます。
PNF効果とは、筋肉の特性を利用した操法になり、筋肉は緊張状態を維持した直後、脱力させると緩むという性質を持ちます。
腰の脊柱起立筋だけでなく、腸腰筋などのインナーマッスルを緩めることができます。
引き寄せにくい脚側を多めに行って、バランスを整えるのもポイントの一つです。
ぎっくり腰から少しずつ動けるようになってからの体操としては、最も効果を発揮させてくれます。
【発症❸日目~❼日目】「お尻ゆるゆる」ストレッチ体操で臀部の緊張をほぐして骨盤を整える

お尻(大殿筋だいでんきん、中殿筋ちゅうでんきん)のストレッチ動画
姿勢体育座りの姿勢から後ろに両手をつきます。
ストレッチ体操方法
①左足を右膝にかけます。脚と胸の間隔を寄せます。
②足と胸の感覚を狭めながらゆっくり息を吐き、15秒間15秒間伸ばします。
③逆の左足も同様に、ゆっくり息を吐きながら15秒間伸ばします。
回数左右交互に15秒×2セット
ポイントお尻の筋肉が伸びている感覚を意識しましょう。
脚を胸のそばに近寄せてできるようになれば、お尻の筋肉が緩んできたということです。
大殿筋の解剖図を動画で簡単解説
ぎっくり腰が発症するとお尻に痺れや痛みを感じる方もいます。
腰とお尻は坐骨神経などでつながっているため、腰を痛めてしまうとお尻にも炎症が広がり固く緊張した筋肉になってしまいます。
この「お尻ゆるゆる」ストレッチ体操で大殿筋、中殿筋をストレッチして伸ばすことができます。
伸ばした時の筋肉の張り具合が左右のお尻で違う場合は、重心がズレ、骨盤のズレが疑われます。
日頃の体重の掛け方、姿勢を改善することも大切です。
二度とぎっくり腰をおこさないための予防策
ぎっくり腰は改善したからといって、気は抜けません。
まずは、痛めてしまった腰のバランスを整えることが大切です。
中途半端にセルフケアをやめてしまうと、また季節の変わり目に同じような腰痛を発生する可能性は高まります。
一度痛めた、腰はクセになりやすいので注意が必要です。
既に、何度もぎっくり腰を繰り返してしまっている人もいると思います。
繰り返すことで腰痛を発症し、数カ月歩けなくなることもあります。
重症化して手術はしたくないものです。そのためには腰とうまく付き合っていかなくてはなりません。
お仕事でどうしても重たいものを持たなければならない人、長時間座っている人はぎっくり腰を繰り返しやすいので痛みが消えてたとしても油断せずにセルフケアを心掛けましょう。
今回ご紹介した体操を定期的に取り入れるだけでも腰の柔軟性が高まりますので、ぎっくり腰をするリスクは減少すると思います。
急性腰痛の症状改善ストレッチは以下の記事でもご紹介しております。
ぎっくり腰のお悩みQ&A
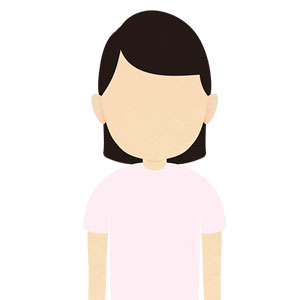
40代 女性
腰が痛くなって1カ月経ちますがお風呂に入ってもいいのですか?

北野 優旗
では、お待たせしました。「股関節すっきり体操」をご紹介します。
1つのストレッチ体操がたった30秒でできます。決して全てする必要もありません。
スキマ時間を利用して、できるストレッチからチャレンジしてみてください。

北野 優旗
一か月痛みが持続しているということは、慢性化しているとお考え下さい。
その場合は、冷やすのではなく、温めて血行を良くしてあげることが大切です。
冷やすと温めるの使い分けは、急性か慢性かです。「急性=冷やす」「慢性=温める」と覚えておいてください。
ゆっくりと体全身を温めて、その後、ゆっくりとストレッチや体操をして筋肉を伸ばしていきましょう。
特に前屈系のストレッチは入念にしましょう。脚をまえ投げ出して、両手で余裕をもってつかめるくらい柔らかくすると腰の痛みが違います。
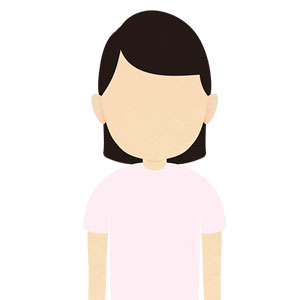
10代 女性
バレーボールの部活動で腰を痛めてしまいました。スポーツ障害の急性の腰痛でもストレッチ体操は効果ありますか?痺れもあります。

北野 優旗
もちろんありますよ!
私も学生時代に腰を痛めて、これらのストレッチ体操をしながらケアしていきました。練習や試合の都合でどうしても無理をしなければならないときもあります。
歩けなくなる前に、できる限りご自身でもケアしてください。
また、足に痺れが来た場合は、練習も試合もストップして小さな腹筋トレーニングで補強していきましょう。
ズキズキ痛みがあれば、監督コーチにしっかりと事情を説明して、部活動を中止する勇気も必要です。
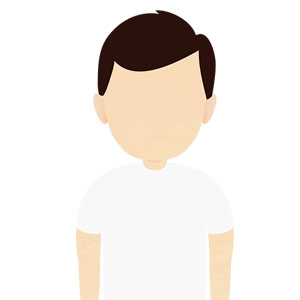
30代 男性
仕事で何度もぎっくり腰をしています。病院は行った方がいいでしょうか?

北野 優旗
もちろん病院でMRIなどで正しく診断してもらうことは大切です。何度も繰り返してしまっていますので急性腰痛の可能性もあります。しっかりと自分の腰の状態を把握しておくことは大切です。正しい症状を知ることで、正しいケア方法が見つかってきますので医師にご相談ください。
ただし、病院にもよりますが、湿布と痛み止め薬で終わることもあります。ご家族やご友人にも相談して病院を決めてから行かれることをおすすめします。
【最後に】まとめ
ぎっくり腰は、誰もが発症してしまう可能性をもっています。
特に運動量が落ちてきた30歳代~50歳代の方に多く見られます。
一日でも早く改善するためには、正しい知識と正しい運動が大切になります。
安静ばかりでもいけません。動かしながらケアしていきましょう。
万が一腰を痛めたときは、今回の記事を参考にして行ってみてください。
また、すでに腰を何度も痛めて、急性腰痛と診断を受けた方には、以下のストレッチ体操の記事がおすすめです。
ぜひ取り入れてみてください。






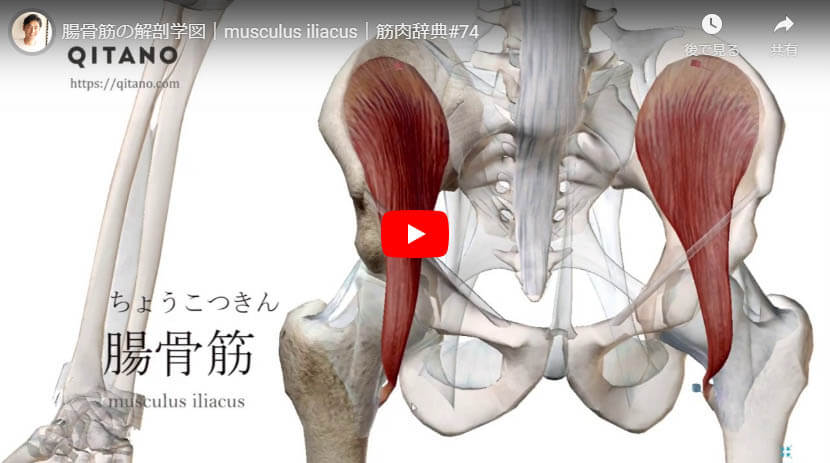

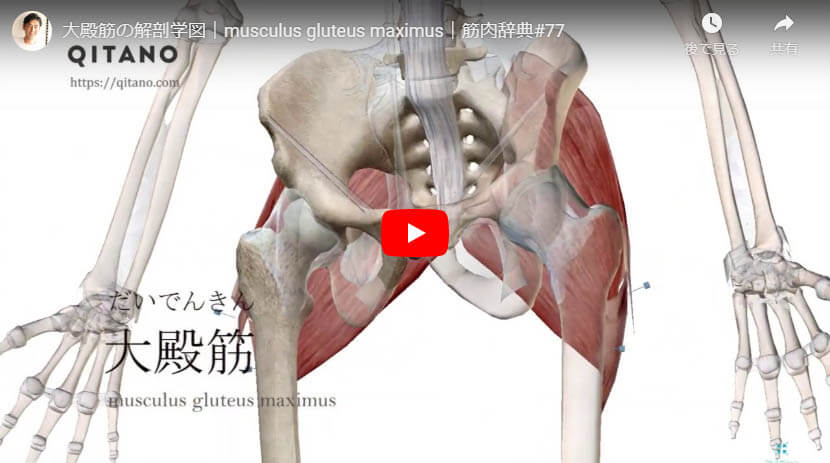
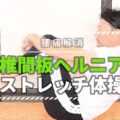
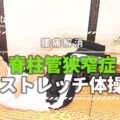
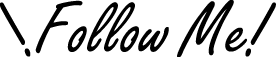
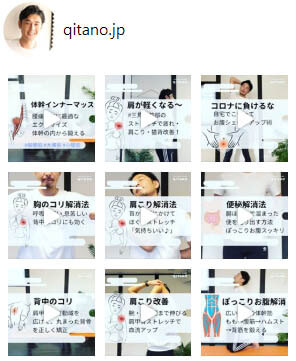

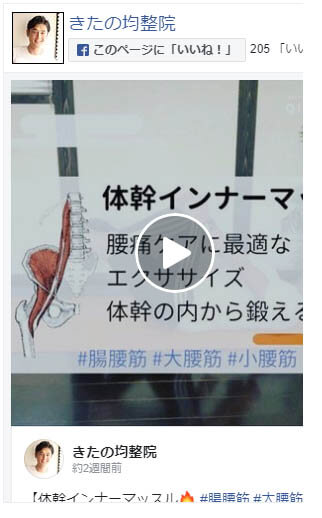


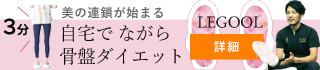
コメント